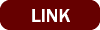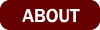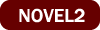-
140文字お題1~5
- 01:最初から最後まで
- 02:それ以上は許さない
- 03:あなたと一緒にいたいんだもん
- 04:逃がしはしない
- 05:貴方の心臓が欲しい 140文字お題6~10
- 06:幸せにするよ
- 07:愛してみろよ
- 08:しゃらっぷ、きすみー!
- 09:ハッピーエンドの来ない悲恋こそ美しい
- 10:だいたいそんなかんじ 140文字お題11~15
- 11:好きにならないはずがない
- 12:いつもの癖
- 13:君という名の
- 14:足して割って、ちょうど
- 15:痛い 140文字お題16~20
- 16:忘れられた指輪
- 17:甘やかせる権利
- 18:残された時間
- 19:頑なに拒む両手
- 20:もう一度、恋をしよう 140文字お題21~25
- 21:境界線の引き方
- 22:50/50
- 23:例外的に
- 24:だいたいあいつのせい
- 25:もしも魔法が使えたならば 140文字お題26~31
- 26:オフレコ
- 27:目を閉じれば
- 28:全部全部、君のせい
- 29:どうにかなってしまいそう
- 30:約束破り
- 31:指切り
11:好きにならないはずがない
氏康は必要以上、己の懐に他人を抱え込むことを良しとしない。己の手に余るもの、手に負えないものがあることを知っている。賢い子犬だ。よもや幼き頃に我と契約して懲りてしまったのではあるまいな…?それならそれで構わぬが。
我は知っている。強面の奥に隠された、優しき瞳の性質の悪さを。
12:いつもの癖
「起きてしまったか。もう少し寝ていれば良いものを」
「う…」
視線が合うと慌てて目を逸らす。事後、疲れて眠ってしまった氏康の後始末をしていた最中だ。さぞ気まずかろうな。
「だから離せと言ったのに」
「…覚えてねぇよ」
耳まで赤い。多分知っているのだろう。切羽詰ると脚を絡めてしまう己の癖を。
13:君という名の
お忍びで町を散策していた最中、立ち寄った茶屋で一匹の子犬がじゃれついてきた。そしてそれを止めようと子どもが走り出てくる。
「こら、小太郎」
「この犬、小太郎っていうのか」
「うん」
「強そうだな」
「え、そうかなぁ…」
ころころした子犬は愛らしい以外の何でもない。氏康は思わず苦笑いした。
14:足して割って、ちょうど
「なんか今イチだな」
果実酒を一口飲み氏康は首を傾げた。
「どれ」
横に居た小太郎が酒を指で掬い取り舐める。
「よく漬かっていると思うが?」
「甘過ぎんだな」
「…何をしている」
「ん?酒足して割ったら美味いかなと思ってよ」
「うぬは甘みよりも酒の味を濃くしたいだけであろう」
「そんな事ねぇよ?」
15:痛い
戦で負傷した傷を幼い氏康が見つめている。その表情は酷く辛そうで、何故だか我の胸は痛んだ。
「その様な顔をするな」
「だって…」
「慣れている」
「慣れちゃだめだよ!…ごめんね、オバケさん」
返事の代わりに頭を撫でても子犬は顔を上げなかった。胸が痛い。子犬の痛みが、我に痛みを思い起こさせる。