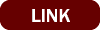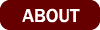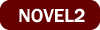- あなたの手 5題
- 01:イタズラな動き
- 02:冷えた僕を暖める
- 03:離したくない
- 04:傷みの残る指先
- 05:その手で触れて
- あなたの目 5題
- 01:見つめ合うたび、
- 02:赤く染まった、
- 03:感じる視線に、
- 04:きらきらと輝いて、
- 05:瞳を閉じて、
- あなたの言葉 5題
- 01:一日中浮かれてしまった
- 02:その言い方は無いんじゃないのか
- 03:無言の言葉が確かに聞こえた
- 04:言葉と気持ち、裏腹
- 05:あの日言われたことを覚えてる
- あなたの体に、
- 01:あなたの体に、溺れる
- 02:あなたの体に、嫉妬する
- 03:あなたの体に、見とれる
- 04:あなたの体に、躊躇う
- 05:あなたの体に、教え込む
「寒ぃと思ったら雪が降ってきやがった」
自室の障子越しに見えた舞う様な影は今年初めての雪だった。
氏康は思わず開けた障子をきっちりと閉め直し、部屋の中央に移動する。火鉢の前に座り込み手をかざすと、じわりとした熱を手の平に感じた。
「小太郎に悪いことしちまったな」
つい今朝方。売り言葉に買い言葉で偵察を命じていた。
上杉と睨み合いをきかせている北の境で今頃は雪に降られているはずだ。
「これじゃあ子犬扱いされても仕方ねぇよ」
誰が聞いている訳でもない部屋で、氏康は項垂れ、独りごちる。
冬を前にして上杉の動きが気に掛かっていた。そのせいで日々苛々を募らせる氏康に対し、小太郎はまだ大丈夫だと軽く言ってのけていた。高を括る様な物言いに納得できず、偵察くらいしてこい、と口にしてしまったのだ。
小太郎は拒否しなかった。
やれやれ、という様に立ち上がり、氏康の頭を一撫して言った。
「仕方のない子犬よ」
「うるせぇな!もう子犬じゃねぇって言ってるだろ!」
「そういう所が子犬だと言っている。だが子犬は子犬らしくしておればよい」
今思えば、天候が崩れることまで読んでいたのかもしれない。だから今、侵攻はないと察していたに違いなかった。
パチパチという炭の爆ぜる音を聞いているうちに、ふと、遠い日の記憶が思い起こされた。
■□■
小田原に雪が降った翌日。
幼かった氏康は一人、足元の悪い道を進んでいた。
まだ幼名を名乗っていて、氏康という名を持っていなかった頃のことだ。当時、小太郎は氏康のことを日常的に「子犬」と呼んでいた。
この頃は実際子どもであったし、周りが懸念するほど武に対して弱々しい子どもだったこともあって氏康はその呼び名を、ごく自然に受けとめていた。
風魔一党の頭領である小太郎は幼かった氏康にとって、父以外で身近にあった大きな存在であり、そんな彼に子犬扱いされても全く嫌だとは思わなかったのである。
その小太郎が何日も城に顔を出さなくなった。
父に事情を尋ねると、風邪を引いた為に幾日かは来られないと言う。氏康は首を傾げた。
(普段から隙など見せないオバケさんがそれほど長く寝込む様な風邪など引くだろうか)
もしそうなのだとしたら、余程の病ではないのだろうか。
そう思った途端、居てもたっても居られなくなった。
氏康は懐に薬の包みを忍ばせ風魔の里へ向かった。供もつけずに外へ出るのも、城を抜け出すのも初めての経験だった。
昼日中にも関わらず上空に広がる雪雲であたりは薄暗く、木枯らしの冷たい日だったことをよく覚えている。
そして初めての冒険劇がどうなったのかというと、結果的に途中の山中で道に迷い凍えていたところを寝込んでいたはずの小太郎に救われ里へ連れ帰られた、という結末に終わった。
後で聞いた話によれば小太郎が城に姿を現さなかったのは任務の為で、その内容が子どもには聞かせたくない類の血なまぐさい任だったため、風邪だと言葉を濁されたのではないか、ということらしい。
「それならそうだって…教えてくれればよかったのに」
氏康は里の屋敷の中で震えながら言った。
先刻温かい飲み物を貰いはしたが、寒さが消え失せたわけではない。
「すまぬ。うぬには言うなと口止めされていた故。城の者たちは皆、うぬを大事にしているからな」
「オバケさんは…父上と、じゃなくて……僕と契約してるんじゃないの」
あれ程心配していた自分だけが蚊帳の外にいた様で面白くない。
お前を心配していたからだと言われてしまえば、何処に苛立ちをぶつけていいのかもわからない。やりきれなかった。
「うぬが怒るのも無理はない。その通りだ。今後は必ず伝えよう」
「どんなことでもだよ」
「約束しよう」
囲炉裏の前に居ても震えの収まらない指先を、大きな手が包みこんだ。背後から体ごと抱きしめられた氏康は驚いて後ろを振り返る。
「少しは暖かかろう?」
「…うん」
「我を心配して、ここまで来てくれたのだな」
「うん」
「うぬは優しいな」
■□■
とても温かな手だった。
あの手を今、自分は敵地に送り冷たく凍えさせている。
「最低だ」
だが落ち込んでいても仕方がない。
小太郎が戻ってきたら、今度は自分が彼の冷えた手を温めるのだ。だから早く。
「早く戻って来い」
念じる様に火鉢の前で手を摺り合わせた。
冷えた僕を暖める