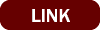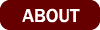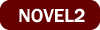- あなたの手 5題
- 01:イタズラな動き
- 02:冷えた僕を暖める
- 03:離したくない
- 04:傷みの残る指先
- 05:その手で触れて
- あなたの目 5題
- 01:見つめ合うたび、
- 02:赤く染まった、
- 03:感じる視線に、
- 04:きらきらと輝いて、
- 05:瞳を閉じて、
- あなたの言葉 5題
- 01:一日中浮かれてしまった
- 02:その言い方は無いんじゃないのか
- 03:無言の言葉が確かに聞こえた
- 04:言葉と気持ち、裏腹
- 05:あの日言われたことを覚えてる
- あなたの体に、
- 01:あなたの体に、溺れる
- 02:あなたの体に、嫉妬する
- 03:あなたの体に、見とれる
- 04:あなたの体に、躊躇う
- 05:あなたの体に、教え込む
まだ陽の高い時刻の室内。
覆い被さってきた小太郎に付き合ってやろうかと、奴の肩布を取り払った時あることに気がついた。この間まで鎖帷子の襟元からはみ出していた傷がない。
「小太郎、肩の傷…消したのか」
「消したが、どうかしたのか」
「いや、どうもしねぇが」
小太郎の体にはあまり傷がない。
大怪我を負うことはあれど細かな傷以外、目立った傷がないのだ。
先日まであった肩の傷も今は跡形なく消えている。どうやって消しているのか、本当にそんなことが可能なのか、よくは分からない。
だが実際に傷は消えている。昔からそうだ。
そして小太郎自身が傷を「消した」と言う理由を、知らない訳ではない。
■□■
俺がその奇怪な現象を知ったのは、数十年も昔、まだ当主になる以前の頃だった。
昔から肌を重ねる関係にあったし、奴の裸体を見る機会など珍しくはない。当時も小太郎の肩には比較的目立つ大きな傷があった。
いつ頃負ったものかは忘れたが、戦の任で負傷した痛々しい痕は見る度に胸が痛んだものだ。
「何故、うぬがその様な顔をする。別に痛くはない」
「お前が傷を負う原因になった戦は北条に責任があるだろ」
「我らには我らの考えがあって北条についている。たとえ北条に責任を求めたとしても、総大将でもないうぬには関係なかろう?」
小太郎は負傷したことについて頓着していない様子だった。
もし責任を求められたとしても、総大将の嫡男というだけで何の力もない俺が責任を負えようもないし、負傷した小太郎に何をしてやれるわけでもない。それは分かっているのだが…己の怪我をまるで気にしない小太郎の在り方はどこか悲しく、やるせない思いがした。
「それでも、気にするなって方が無理だ」
「うぬは優しいな」
小太郎はそう言って、いつもの様に俺の髪を撫でた。
そんなある日、小太郎に在ることが当たり前だった傷が消え失せていた。
俺は傷が無い事実に驚愕した。
驚きと同時に沸き上がってきたのは、この小太郎は本物の小太郎なのか、という疑念だ。今、目の前に居る男は他の忍びが化けている偽物かもしれないという思いと同時に、もしかしたらこの小太郎が、小太郎ではあれ己の知る昨日の小太郎と同じではないのかもしれない、という疑念が重苦しく渦巻いた。
それは互いに思うところはあれど口に出せないでいる現実。
代替わりという、以前味わった喪失に対する恐怖だった。
「…オバケ、さん?」
「どうした子犬」
俺は完全にその恐怖に呑まれていた。
伸ばした指先が情けないほどに震えている。
消えた傷痕を辿った指先の意味を小太郎は察した様だった。
「我が偽者だとでも思うたか?」
小太郎の手が頭を撫でる。
その慣れ親しんだ手つき、力加減、仕草。それは間違えようもない小太郎のものだった。もし別人であるのなら絶対に気付ける。それだけは自信があった。
涙が零れそうなほどに安堵した俺は思わず小太郎にしがみついていた。
「傷が、なくなってるから」
「無くて困ることはなかろう?あの様に目立つ傷は我の任の邪魔になる。だから消した。それだけのことよ」
「? 邪魔って…なんだよ?」
「……印象に残り易い傷、ということだ」
小太郎は言葉を濁す様に、それ以上言わなかった。
■□■
「なぁ、前から思ってたんだけどよ。お前、他所で関係した奴の印象に残りそうな傷は消してるんだろ? その背中の痕は消さないのか」
小太郎は聞き終えた途端、クク、と小さく笑う。
「我が言葉を濁しているというのに、随分とあからさまな言い様をするものよ」
だからなんだ、と睨んでみせるが、小太郎は動じない。
間諜の任で出向いている際、小太郎が何をしていようが俺の知るところではないし、他の誰と関係を結んでいようが奴の自由だ。諜報目的でそういうことになることも理解出来なくはない。
そんなことは解っている。
自分にだって妻もいるし、子どもも居る。
小太郎に想い人が居ようとも不思議ではないし、家族が出来るのなら祝ってやらなければ、とも思う。
だが、本当に手放しに喜べるのかと言われたら…、答えにつまる。
「不機嫌な物言い、といった方がよいか?」
「別に不機嫌じゃねぇよ」
「何を邪推したのかは知らぬが、我は氏康のものだと言っておろう。背中の傷など目立たぬし、そうそう見られることはない故、消さぬ」
「ふーん」
「うぬはよく見ているのだな」
「ま、……真昼間からこんなことしてりゃあな」
確かに俺ですら小太郎の背中を見ることはあまりない。薄暗い閨の中での話なら、背中の傷など他者が記憶に残すようなことなどそうそうないだろう。
奴が言う通り大きな傷ではないけれど、すぐに察しがつく…爪の痕。俺の知らない、小太郎の傷。
消さぬとはっきり言ったのだから、それなりに思い入れがあるということだろうか。戦でついたものではない、その傷痕に俺は…嫉妬していた。
(なにが俺のものだ)
風をつかむことなど誰にも出来ぬ。
小太郎の言うとおり、この男は誰も飼いならすことなど出来ない。
そう思っていたのに背中に傷をつけた何者かは小太郎という男を掴んでいるのかもしれない。
いっそ思い切り爪でも立ててやろうか。
そんな不穏な考えが浮かんだ時、
「うぬが何十年も前につけた痕など、他の者が気付くことはまずなかろう」
小太郎に言われた意味がよくわからなかった。
「今、なんて言った?」
「何を思い違いしているのかは知らぬが、これをつけたのは、数十年前のうぬだ。……氏康?」
急激に顔に血が上る感覚を、俺は口も聞けぬまま感じていた。
あなたの体に、嫉妬する