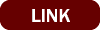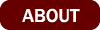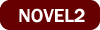01
「氏康、風邪を引いた」
そう言って、毎日の様に俺が開設している内科の医院へやってくる男がいる。奴の名は風魔小太郎。飛びぬけて背の高い、赤毛の派手な男だ。
「お前、日頃から顔青いもんな」
「だから風邪だと言っている」
(勝手なこと言うんじゃねぇや)
風邪か決めるのはこっちの仕事だ。
そして俺の診断では、こいつは間違いなく風邪など引いていない。
暇潰しなのだろうか。それとも新手の嫌がらせか?
どちらにせよ、そんなことの為に寒空の下を出かけてくるなんて馬鹿げている。思うところはあれど、その真偽は分からぬまま小太郎が此処へ通う様になって数ヶ月が過ぎていた。
「まぁ俺の見立てじゃあ大丈夫そうだからよ。家で温かくしてゆっくり休め。お大事にな」
「わかった」
そんな会話が毎日繰り返される。はっきり言って異常だ。
ある日に至っては、休診日である日曜にも関わらず小太郎はやってきた。
「何だよ、また風邪か?」
「今日は違う。切ったのだが」
差し出された右手の指先には僅かに血が滲んでいた。
「ド阿呆!うちは内科だって言ってんだろ!だいたい今日は休診日だ。そんなもん絆創膏でも巻いときゃいいだろうが。帰れ」
「氏康」
「何なら外科への紹介状でも書いてやろうか?」
嫌味を言って背を向ける。
それ以上なにも言ってはこないが出て行きもしない小太郎を振り返ると、上背を丸めるように腰掛けたままションボリと俺を見ていた。
「……仕方ねぇ奴だな」
別にその姿が微笑ましかったとか、愛らしかったとか、そういう類の感情はない。どのみち何かしてやらなければ、こいつは出て行かないのだ。
俺は溜息をつくと、診察室の奥に置いてある置き薬の箱から絆創膏を取り出し、指に巻いてやった。
「これで満足かよ」
「あぁ」
こうしてやれば素直に帰っていく。
だが、いい加減勘弁して貰いたかった。その時。小太郎の手が俺の頭を撫でた。
「おい、何しやがる」
「氏康は優しいな。では、また来る」
不意打ち過ぎて何も出来なかった。
頭を撫でられるなど、いつ振りのことだろう。その懐かしい感触にドキリとした。そして小太郎が出て行ってから暫くして思う。
「やっぱり、また来るのかよ…」