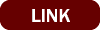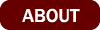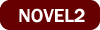03
風邪の患者も多いこの季節だ。
まさか診察室や待合で食事する訳にもいかず、小太郎を住居スペースである二階へあげることにした。ダイニングに通してやり、そこに座ってろと言うと小太郎は頷き、きょろきょろと周りを見回している。
「ほら、茶」
飲み物だけ用意して向かい合わせでテーブルを挟んだ。
一人暮らしだから食卓として使うような立派なテーブルなど置いてはいない。狭い机上は料理を並べただけでいっぱいになった。俺は差し出された箸を受け取り、料理に箸を伸ばしながら尋ねてみた。
「さっきお裾分けって言ってたな。どういう…」
「少々作りすぎたのでな」
「これ、お前が作ったのか?」
「そうだ」
「へぇ」
少々という言葉に引っかかりつつも、見かけによらないものだと思う。しかも料理は見た目だけでなく実際に美味しかった。
「意外に器用なんだな。で、なんで俺に?絆創膏の礼のつもりか?」
「カップ麺しか食っておらぬのかと思ってな」
思わず持っていた箸を落としそうになった。確かに昨日の晩飯はそれだった。疲れていたし、自炊するのが面倒だった。それよりも、だ。
「なんでお前がそれを知ってる」
「クク、何故でしょう」
狭いテーブルのせいで互いの距離が近い。
そして小太郎は俺から目を逸らさない。
人をくった様な笑みと物言い。目の前の男がひどく不気味に感じられた。
言葉を失っていると小太郎は突然すっと視線を逸らし窓を指す。
「昨日、通りかかった時に見えた」
当たり前の答えだった。
一瞬、何を想像していたのだろう。
それもこれも小太郎が毎日病院を訪ねてくる理由が分からないせいだ。
いい加減その理由が気になって仕方がない。
「お前さ、なんで毎日通ってくるんだよ」
「風邪なのでな」
「真面目に答えろ」
小太郎の手がぬっと目の前に伸びる。
差し出された箸には出し巻き卵が摘まれていた。
「冷めるぞ?口を開けよ。ほら、あーん」
「ド阿呆!自分で食える!」
結局はぐらかされ、小太郎の答えを聞くことは出来なかった。