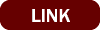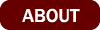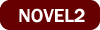05
「随分と苦しそうだな」
寝入ってからどれくらい経ったのか。
寒気に目が覚めると、目の前に小太郎が居た。
「お前…っ!? どっから入り込みやがった」
「鍵が開いていたぞ。物騒な事よ」
鍵を…閉めなかっただろうか。
閉め忘れたのだとしても、室内がまだ暗いこんな時間に小太郎が居ることの方がおかしくないか。
ぼんやりとした頭で思索していると小太郎の手が伸びて来て頬に首筋に、と触れられる。
「離れろ、インフルエンザだ」
「ほぅ?」
小太郎は驚いた様子もなく、それどころかますます手を這わせてきた。
「熱が高いな」
「帰れっ」
「弱った子犬を捨て置けと?」
触れられている部分がピリピリとする。
「ひどい汗よな。我が着替えさせてやろう」
小太郎は勝手にクローゼットを開けて着替えを持ち出し、力任せに俺の体を転がすと着ている寝間着のボタンを、これまた勝手に外し始めた。
「おい、寒ぃぞ…」
「すぐに部屋を暖める。我慢せよ」
感染すかもしれない。近づくな。そう思うのに、熱のせいかだんだんと抵抗する気力が無くなっていく。
されるまま着替え、布団をかけ直され…そのうちに、まぁいいかという気になっていた。寄るなと言っても引き下がらないことは分かっている。それならば、おとなしく看病を受けて少しでも早く帰って貰った方がいい。
部屋に暖房が効き始めた頃、階下へ下りていった小太郎が水のペットボトルを片手に戻って来た。
「飲め、脱水を起こす」
俺の目の前に差し出して見せ蓋を開ける。受け取ろうとした手を無視し、小太郎はそれを煽り飲んだ。なんでお前が飲むんだよ、そう思った瞬間、
「む…ぅ…?!」
唇に食いつかれた。息が苦しい。俺は何をされているんだ…。
異常な近さに居る男の所業に熱で浮かされた頭がついていかない。
どうにもならず、口移しで流し込まれた水を飲み込んだ後、瞬発的に物凄い力が出た。
「っ…このっド阿呆!インフルエンザ感染するって言ってんだろ!」
小太郎を跳ね飛ばし、跳ね飛ばされていった小太郎の口元をごしごしと拭く。
「下に行って、うがい手洗いに消毒して帰れ!仮病とは言え、てめぇは俺の患者だぞ。二次感染なんて絶対にさせたくねぇ!」
激しく動いた反動か、立ち上がろうとしたら眩暈で後ろに倒れるかと思った。這う様によろよろとベッドへ引き返し、布団を被る。
「…もしもの場合は駅前の総合病院行ってくれ。もう、帰れ」