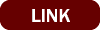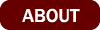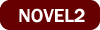06
寒い、痛い、怠い。
暴れたのがまずかったのか、症状は更に悪化した。
小太郎はまだ居た。追い返したくとも、もう起き上がるのもつらい。
「39度5分か。インフルエンザの薬は飲まぬのか」
「ありゃあ48時間以内に飲まねぇと大した効果でねぇんだ。うちは薬出してねぇし、薬局が開くの待ってる間に過ぎちまうだろ。寝てりゃ治るしよ」
「ここまで熱が高くては辛かろう?」
確かに患者がこんな状態ならとっくに解熱剤を処方している。解熱剤を使えばインフルエンザを長引かせることにはなるが、高熱が続くのは苦しいだけだ。
「下に…置き薬の箱がある。持ってきてくれ。前、お前に絆創膏出してやった箱だ」
「わかった」
小太郎はすぐに階下へ行き、箱を掴んで戻ってきた。
だが、箱から出された薬を見て、俺は首を横に振る。
「ダメだな」
「ダメとは?」
「インフルエンザに…アスピリン系の解熱剤は…まずいんだ。飲めねぇ」
「何なら良いのだ」
「アセトアミノフェン系か…イブプロフェン系…っていっても分かんねぇか。いや、買いに行ったりしなくていいからな?もう一度寝たら下がる」
小太郎は箱をまだガサガサと探っていたが、俺はもう疲れていた。
どの道、寝ていたら治る。いざとなれば自分で点滴も打てる。大丈夫だ。そう思いながら目を閉じる。
「結局、面倒看させちまって悪かったな、。もういいからお前は帰…」
「本当にそう思っているのか?」
「? なんだって?」
「我はもう何も出来ず、うぬのこの様な姿を見るのは嫌だ」
いつもとは違う、寂しげな声だった。
小太郎の様子に異変を感じ目を開ける。
「悪いと思っているのなら大人しくしておれ」
何を、と思っている間に体を反転させられ、真上から押さえつけられた。寝技のようにして自由を奪われる。
そのまま下着ごとズボンをずり下ろされて血の気が引いた。
「お、おい?!何しやがる…離せ!」
ズボンを上げ直そうとしたが、押え付けられている力が強すぎて腕も回せない。
(こいつ、こんな怪力だったっけか!? いくら俺の体が弱ってるって言ったって…)
そんなことを思った次の瞬間、最大級の失望が俺を襲った。
「ぐぇっ!」
「色気のない声よな。うぬの言っていたアセトアミノフェン…座薬ならあったぞ。少しの間、耐えよ」
後孔を抉じ開ける様に指を突っ込まれ、身動きが取れない。
気持ち悪さに体が震え、その指を拒絶しようと体が強張る。
「うぐぅ…」
「氏康、力を抜け。薬が入らぬ」
薬さえ入ればこんな責め苦から解放される。
そう分かっていても自らすすんで他人の指を受け入れるのは困難で、力の抜き方が全く分からなかった。