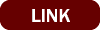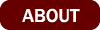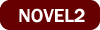07
「うぅっ…うーっ!」
子どもが嫌嫌をする様に首だけを動かし拒絶する。
「仕方のない子犬よ」
「っ…!?」
小太郎は協力が得られないと分かると器用に俺の腕を押さえ込んだまま手を前に回し、なんの躊躇いもなく俺のものを掴むとそのまま扱き始めた。
それと同時によく分からないことを言い始める。
「氏康。男は死に掛けている時にでも勃つというのは本当か」
「…は?」
「うぬは内科医であろう。どうなのだ」
今、そんなことを問答する状況だろうか。
頭の中は混乱していく一方だが…小太郎が大真面目な顔で囁いてくる為、思わず返してしまった。
「そりゃ…場合に因るだろ…体が参っちまってたら…普通は勃ちやしねぇよ」
「では、うぬも参っているのだな?」
「んぅっ…あ、あぁ…」
「そうか」
それよりも手を止めろ。
なんでお前の手で勃たなきゃならねぇと言いたい。
小太郎は気の毒そうに頷いたが、本来の目的を忘れた訳ではなかったらしい。少し力が抜けた隙に、指を奥へ奥へと進めてきた。
「いい子だな」
「ぃ…っ!」
小太郎が指を動かすたび、異様な感覚が襲ってくる。
唇を噛みしめ、どうにか喘ぎをこらえるが、やがて体が勝手にびくびくと震えだした。おかしな声が漏れそうになり布団を握り締め堪える。
もう十分だ。それ以上奥へ入れる必要はない。薬だって溶け始めているだろうが!
そう思ったが小太郎に止める気配はない。
「も、もう抜け!痛ぇよ!」
「慣らしてやれず、すまぬな」
見当違いな謝罪だ。噛み合わない会話が心底つらい。
(違う!そういう問題じゃねぇ。だいたい慣らされてたまるかよ…。なんでこんな事になっちまったんだ。内科医のくせにインフルエンザなんてかかった俺が悪いのか…?やっぱり何としてでも追い出しておくべきだった。さっきの悪ぃな云々は取消しだ。恥ずかしさで顔から火でも噴きそうだ。いや、もう…泣きたい)
心の中で不甲斐ない自分を責めながら、必死に気を逸らす。
「まだ、痛いか?」
溶け始めた薬が潤滑剤の効果をもたらしているのか、既に痛みはない。
ただ、別の感覚に翻弄され続けていた。
(頼む、それ以上触らないでくれ…っ!)
熱で参っていると言ったのに勃ちそうだった。
当たり前だ。体の内側から前立腺を刺激されているのだ。嫌でもそうなる。
「も…勘弁……してくれ」
荒くなってくる息と、滲んでくる涙を堪えながら訴えると、小太郎はじっと俺を見ていた。そのなんと表現したらいいか分からない視線の強さに思う。
(この状況、マズくねぇか…?)
ごくり…と恐らく双方違う意味で喉が鳴った。
そして、あっ…と思った瞬間、小太郎が圧し掛かって来る。明らかな身の危険を感じた。